🎧「訳が分からん!」から始まる、第三の学びの呼吸
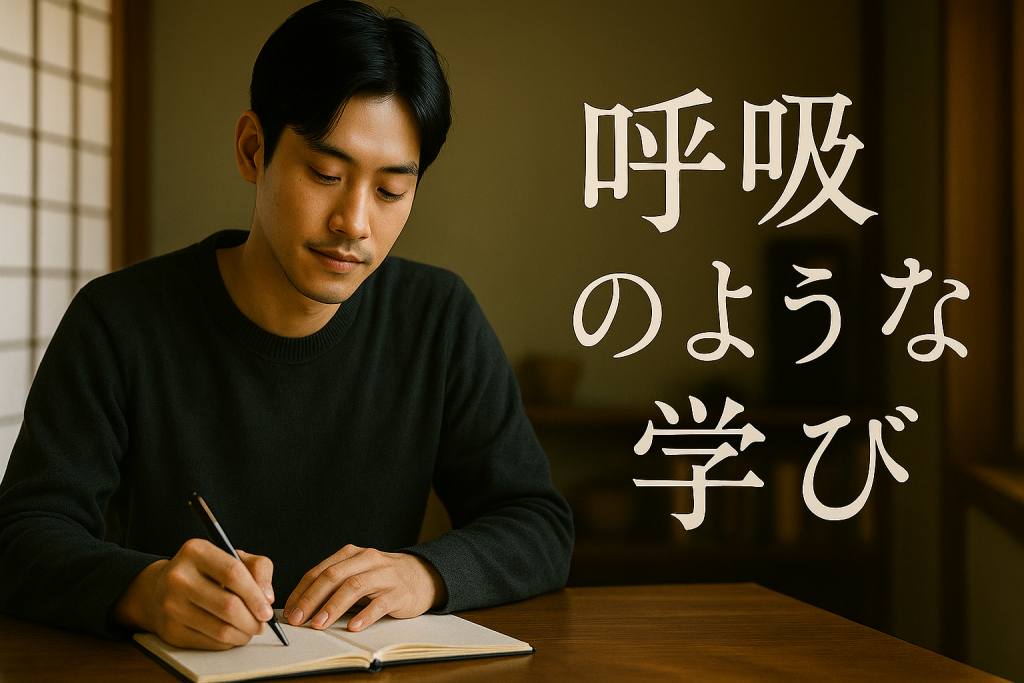
序章 「……もう、訳が分からん!」
数日前のプログラミング勉強会でのこと。
新人がGitとGitHubの使い方に苦戦していた。
その姿に、かつての自分を重ねた。
あの頃の僕も、まさに「訳が分からん!」の真っ只中だった。
でも、あの混乱の中に、なぜか “すごいことができそうだ” という予感があった。
理解していないのに、なぜか惹かれる。
手探りで動かしながら、少しずつ形になっていく。
気づけば、「あのときの“訳の分からなさ”」が、
いまの自分を支える土台になっていた。
第一章 わからないまま動く——“動の知”
学びは、理解からではなく、動きから始まる。
僕がAIや統計を学びはじめた頃もそうだった。
理屈を知らなくても、とりあえず動かしてみる。
- ChatGPTに売上予測をお願いしてみる
- AIの画像認識をコピペで動かしてみる
「うわ、動いた!」というあの瞬間の感情は、
あとで理論を学ぶときの灯になる。
“動の知”とは、理解ではなく感動で始まる知。
驚きが、学びのエンジンになるのだ。
第二章 あとから染みてくる——“静の叡智”
少し時間が経って、理論書を読むときがある。
そのページの中に、かつての自分の体験を見つける。
「あ、これ、あのとき自分がやったことだ。」
その瞬間、数式が人間味を帯びる。
知識が、あの時の感情と結びついて生きた経験になる。
これが“静の叡智”。
動いた経験を、内省の中でゆっくり熟成させる時間。
第三章 動と静の往復——“第三の呼吸”
ヨーロッパのAI教育では、ハッカソンのように「まず試す」文化がある。
それが“動の知”。
一方で、日本には「丁寧に整える文化」がある。
それが“静の知”。
どちらか一方だけでは、息が詰まってしまう。
必要なのは、動と静の往復。
「まず試す」「あとで考える」。
このリズムこそ、リスキリングの閉塞を解く第三の呼吸だ。
それは制度に与えられた学びではなく、
自分でつくる “生きるための学び” である。
結章 訳が分からないからこそ
新人の「訳が分からん!」という一言を聞いて、ふと思った。
——“訳が分からない”と言える人は、すでに動き出している。
驚き、混乱し、試しながら少しずつ慣れていく。
その積み重ねが、未来の知恵になる。
だから、焦らなくていい。
動きながら、静まりながら、自分のペースで往復すればいい。
学びは呼吸。
息を止めず、今日も自分のリズムで進めばいい。
🪞 行動の一歩
- 「訳が分からん!」と思った瞬間をノートに一行メモする
- 3日後に読み返して、“何か少し分かったこと”を一言書く
- それがあなた自身の「第三の呼吸」の記録になる
💡おまけのひと言
もし今、何かに苦戦しているなら、
それは「わからない」ではなく、「わかろうとしている」証。
その瞬間こそ、学びの始まりなのです。
📖 Noteで読む
🎧 Spotifyで聴く
▶️ YouTubeで見る
📘 Facebookで読む
🪷 Instagramで見る
🕊️ Xで読む